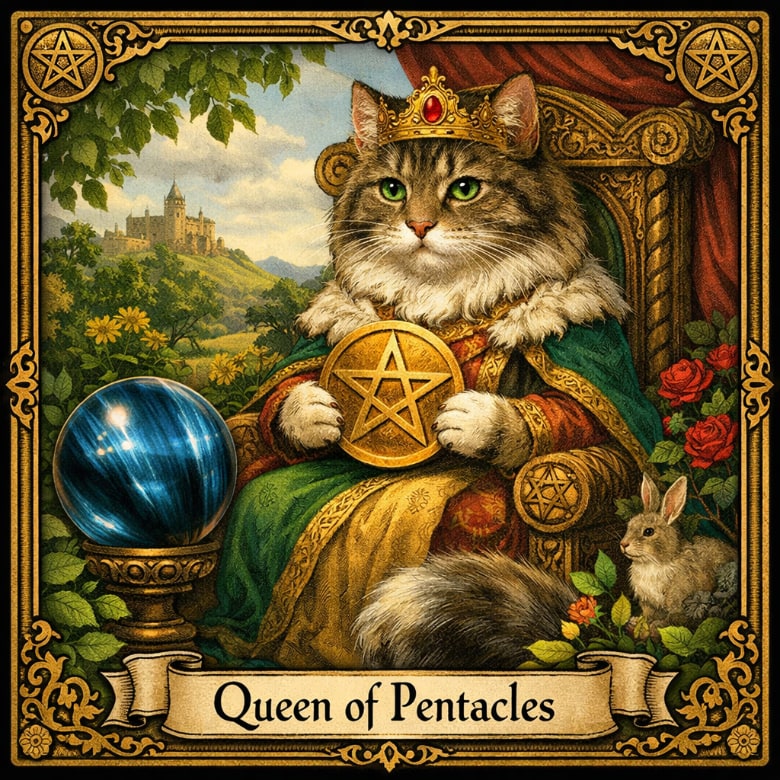スタッフの友次郎です。
2月17日の甲府は一日ほぼ曇り。
曇ってしまうと気温が上がりません。朝9時台で4℃。最高7℃程度でしょうか。
風がなく穏やかなので気持ち良い寒さ。そうそう、予報が外れて雨はなし。いつもコレです。
■ ワンドの騎士」が告げる迷いを断ち切る前進力
カードは「ワンドの騎士」

このカードは、情熱と行動力の象徴。炎のエネルギーをまとい、目的に向かって一直線に駆け抜ける存在です。
慎重さよりもスピード、迷いよりも決断。考えすぎて動けなくなるよりも、まず一歩を踏み出すことの大切さを教えてくれます。
今回のリーディングでは、「迷いと退路を断ち前進あるのみ。自分で運命を切り開く勇気を持とう。優柔不断を捨て即実行が大吉。」と読み解きました。
ワンドの騎士は、チャンスを前に立ち止まることをよしとしません。完璧な準備を待つよりも、情熱が熱いうちに動くこと。
たとえ途中で軌道修正が必要になったとしても、走り出さなければ景色は変わらないのです。
今は守りに入るときではなく、攻めの姿勢で未来をつかみにいくとき。自らの選択に責任を持ち、堂々と旗を掲げて進みましょう。
そして、この力強い流れを後押ししてくれるパワーストーンが「ルチルクオーツ」。

透明な水晶の中に金色の針を宿すこの石は、まるで内側から光を放つ情熱そのもの。停滞した空気を打ち破り、勢いと積極性を高めてくれるといわれています。
決断したのに最後の一歩が踏み出せないとき、ルチルクオーツは背中を押し、行動へと導いてくれるでしょう。
また、ルチルクオーツは「あきらめない強さ」を育てる石でもあります。
挑戦の途中で壁にぶつかっても、情熱の火を絶やさず前を向き続けるサポートをしてくれるのです。
ワンドの騎士のエネルギーと共鳴し、思いを現実へと変える推進力を与えてくれる存在といえるでしょう。
迷いを断ち、情熱に火を灯し、すぐに動く。今こそ、あなたの内なる騎士を目覚めさせるときです。ルチルクオーツの輝きを胸に、運命を自らの手で切り開いていきましょう。
■ 2月18日 忍野方面へ
忍野八海、新倉山富士浅間神社などを回る予定です。
ここ、甲府市池田からだと一般道で1時間と少しくらい。コンビニでおにぎりを買って出発します。
明日が良い日になりますように。